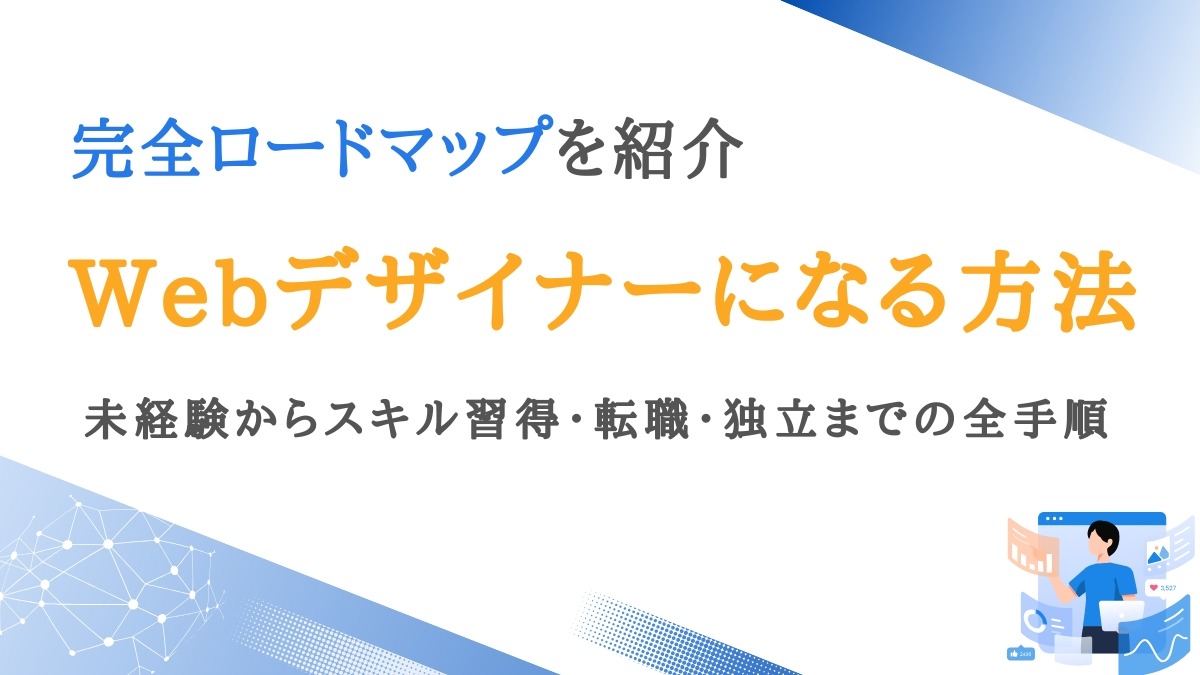Webデザイナーは、在宅・副業・フリーランスといった柔軟な働き方ができる職種として、近年ますます注目を集めています。
しかし、未経験からWebデザイナーを目指すには「何から始めればいいの?」「本当に就職や副業はできるの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、デザインスキルやコーディングの知識、ポートフォリオの作成、そして仕事の探し方など、学ぶべきことは多岐にわたります。
そこで本記事では、未経験からWebデザイナーとしてスキルを身につけ、転職・副業・独立に至るまでの全ステップを完全解説します。学習方法の選び方や効率的な転職方法、案件の獲得法や年収の実情など、実践的な情報を網羅。
「自分にもできるか不安」「何から始めたらいいか分からない」という方に向けて、順を追ってわかりやすくご紹介します。
Webデザイナーというキャリアを現実のものにするための具体的な道筋を、ぜひ本記事で確認してみてください。あなたの一歩が、新しい働き方と人生を切り拓くきっかけになるはずです。
※本コンテンツはプロモーション(PR)を含みます。また、詳しい最新情報に関しては必ず公式サイトをご確認ください。料金は特段の表示がない限りは全て税込表記です。
Webデザイナーとは?仕事内容や将来性を解説

Webデザイナーとは、Webサイトやアプリケーションの見た目や使いやすさを設計・デザインする職種です。
企業や個人のホームページ、ECサイト、採用ページ、LP(ランディングページ)など、あらゆるWebコンテンツの「第一印象」や「ユーザー体験」を左右する役割を担っており、デジタル時代において欠かせない存在です。
Webサイトの目的やターゲットに応じて、配色やレイアウト、文字の大きさ、余白のバランス、導線の配置などを工夫しながら、視覚的な訴求力と機能性を両立させることが求められます。
①Webデザイナーの主な仕事内容
Webデザイナーの仕事は「見た目を整えること」に留まらず、目的達成のために設計されたデザインを制作するという広範な領域に渡ります。
具体的な業務としては、まずクライアントやディレクターとの打ち合わせからスタートし、要望や目的をヒアリングした上で、ワイヤーフレームやデザインカンプ(完成イメージ)を作成します。
その後、PhotoshopやIllustrator、Figmaといったデザインツールを使用してビジュアルデザインを形にし、必要に応じてHTML/CSSを使った簡単なコーディングまで対応することもあります。
また、サイト全体のトーン&マナーを整えたり、レスポンシブデザインに対応したスマホ版のUIを設計したりと、多岐にわたる役割を担います。
案件によっては、バナーやロゴの制作、アイキャッチ画像の作成、WordPressでのデザイン組み込みなども含まれるため、幅広い知識が求められます。
②Webデザイナーとコーダー・UI/UXデザイナーとの違い
Web業界には、似たような職種名が多く存在し、特に混同されやすいのが「コーダー」や「UI/UXデザイナー」との違いです。
コーダーは主に、Webデザイナーが作成したデザインをもとに、HTML、CSS、JavaScriptなどを用いて実際のWebページを構築するエンジニア寄りの職種です。ビジュアルよりも構造や動作に重点を置くのが特徴です。
一方、UI/UXデザイナーは、ユーザーインターフェース(UI)やユーザー体験(UX)に特化した設計を行う専門職です。
ボタンの配置やナビゲーションのわかりやすさ、ユーザーの心理的動線などを重視し、見た目というより「使いやすさ」や「成果を出す構造」を設計する点にフォーカスしています。
Webデザイナーはその中間的な役割で、ビジュアル面を中心にしながら、ある程度のUI/UXの視点やコーディング知識も兼ね備えていることが理想とされます。
最近では、それぞれの職種の境界が曖昧になりつつあり、WebデザイナーにUI設計や簡単なコーディングスキルが求められるケースも増えています。
③今後も需要はある?Webデザイナーの将来性
Webデザイナーという職種は、デジタル化の進行とともに今後も安定した需要が見込まれる分野の一つです。
ECサイトやSNS、アプリなど、あらゆる情報発信がWebを通じて行われる時代において、「デザインの質」がユーザーの行動や売上を大きく左右するようになっています。
特に、スマホファーストやUI/UXの重要性が高まる中で、視覚的な表現力に加えてユーザー視点での設計力が求められており、Webデザイナーの存在価値はむしろ増しています。
加えて、副業やフリーランスという働き方の多様化により、企業の業務委託・外注需要も拡大しています。大手企業だけでなく、個人事業主や中小企業までもがWebサイトの改善・刷新に投資する傾向にあるため、案件の幅も非常に広いのが特徴です。
一方で、AIによる自動デザインやノーコードツールの台頭により、単純作業の一部が代替される懸念もあります。
ただし、ユーザーの感情やブランドの文脈を読み取り、表現に落とし込む力は人間にしかできない部分でもあり、「考えるデザイナー」「設計できるデザイナー」には今後も大きな需要が見込まれます。
つまり、Webデザイナーはただ作れるだけではなく、「設計できて伝えられる人材」になることが、今後のキャリアアップにも直結すると言えるでしょう。
Webデザイナーになるには?未経験から目指すための5ステップ
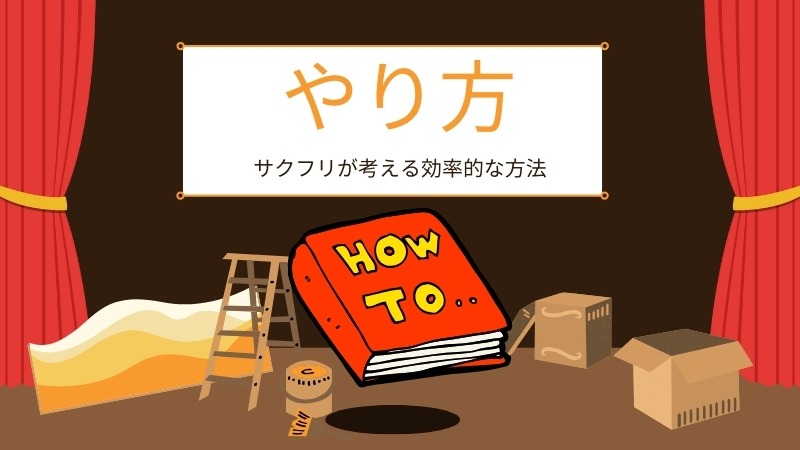
Webデザイナーを目指す際、多くの人が「何から始めればいいのかわからない」と感じるのではないでしょうか。
特に未経験者にとっては、スキルの習得から実績づくり、仕事の獲得まで、多くのステップが必要になるように見えます。
しかし、段階的に学んでいけば、着実にスキルを身につけて仕事につなげることが可能です。ここでは、未経験からWebデザイナーを目指すための5つのステップを順を追って解説します。
①Webデザインの基礎を理解する
最初のステップは、Webデザインの基礎的な考え方や役割を理解することです。
Webデザインとは、単に「見た目を整える」ことではなく、ユーザーにとって見やすく、使いやすい画面を設計することに本質があります。
ターゲットユーザーが誰なのか、どんな目的でそのWebサイトを見るのかといった点を踏まえた上で、レイアウトや配色、フォント選びなどを考える必要があります。
この段階では、まず「Webデザインとは何か」「どんな構成要素があるのか」「基本的なWebサイトの構造とは」など、概念的な部分からインプットを始めましょう。
YouTubeやブログ、Webデザインの入門書などで全体像を掴むことからスタートするのが効果的です。
②必要なツールやソフトを使えるようにする
基礎知識を得たら、次は実際に手を動かして、デザインツールに慣れていく段階です。Webデザインにおいて代表的なツールには、以下のようなものがあります。
- FigmaやAdobe XD:ワイヤーフレーム・UI設計に使う
- PhotoshopやIllustrator:ビジュアルデザインや画像加工に使う
- VS CodeやBracketsなど:HTML/CSSを編集するためのエディタ
特にFigmaは現在多くのWeb制作現場で導入されており、初心者でも無料プランから使えるためおすすめです。
ツールの基本的な操作方法やショートカット、テンプレートの活用などを学びながら、少しずつ制作物を作ってみましょう。
「使える」状態ではなく、「自分の思い通りにデザインを形にできる」状態を目指すのが理想です。
③実践的なデザイン制作に挑戦する
ツールの操作に慣れてきたら、次は実際のデザイン制作に取り組んでいきます。
最初から複雑なWebサイトを作る必要はなく、「架空のカフェのLP」「自己紹介サイト」「採用サイト風のトップページ」など、自分の興味のあるテーマから取り組むのが良いでしょう。
このステップでは、単に真似して作るのではなく、「なぜそのレイアウトになっているのか」「どうすればもっと使いやすくなるか」など、考えながらデザインすることが重要です。
また、実際の現場ではスマートフォン対応(レスポンシブデザイン)が求められるため、PC版とスマホ版の両方を意識して作る癖をつけておくと実践力が身につきます。
さらに、コーディングも並行して学んでおくと強みになります。HTML/CSSの基礎や、簡単なJavaScriptの実装まで覚えておくと、デザイナーとしての幅が広がり、採用や案件獲得に有利になります。
④ポートフォリオを制作してスキルをアピール
一定の作品ができてきたら、それらを一つにまとめた「ポートフォリオサイト」を制作しましょう。
ポートフォリオは、あなたのスキルやセンス、思考力を可視化するための最も重要なツールです。企業への応募時や、副業・フリーランスとして営業する際にも必須となるものです。
ポートフォリオには、以下のような要素を含めると評価されやすくなります。
- サイトの目的やターゲット、制作の意図などを説明
- ワイヤーフレームやデザインの遷移なども掲載すると説得力が増す
- スマホ対応やSEOなどへの配慮があればなお良し
- 自己紹介や連絡先も忘れずに
WixやSTUDIO、WordPressなどのノーコードツールを使えば、コーディングが苦手でも公開可能です。作品数は最低でも3〜5つ以上あると説得力が増します。
⑤転職・副業・独立などの進路を決める
スキルとポートフォリオが整ったら、いよいよ実際に仕事へとつなげるステップです。目指す働き方は人それぞれですが、以下のような進路が考えられます。
- 正社員として企業に就職する
→安定した収入と実務経験を得たい人におすすめ - 副業としてクラウドソーシングで案件を受ける
→本業を持ちながら収入を増やしたい人に最適 - フリーランスとして独立する
→自由度の高い働き方を求める人向け
転職を目指す場合は、Webデザインに強い転職エージェントを活用すると、未経験歓迎の企業を紹介してもらえるケースも多くあります。
副業の場合は、クラウドワークスやココナラ、ランサーズなどのプラットフォームを活用して実績を積むのが効果的です。
また、フリーランスとして独立を目指す場合は、税務知識や営業力も必要になるため、徐々に副業→独立という流れを取るのが安全です。
Webデザイナーに必要なスキル一覧|学ぶ順番と学習方法

Webデザイナーとして活躍するには、デザインソフトを扱うスキルだけではなく、UI/UXやコーディング、さらにマーケティング的な視点まで、さまざまな知識と技術が求められます。
ここでは、未経験からWebデザイナーを目指す上で必要となる主なスキルを5つに分類し、それぞれの学ぶ順番と学習方法について詳しく解説します。
①デザインスキル(Photoshop、Illustrator、Figmaなど)
Webデザイナーの核となるのが、ビジュアルを作り上げるためのデザインスキルです。
PhotoshopやIllustrator、Figmaなどのツールを使いこなせることはもちろん、配色やタイポグラフィ、レイアウト、視線誘導といった「視覚的に美しく、使いやすい」デザインの基本原則を理解しておくことが重要です。
Photoshopは画像加工やバナー制作に強みがあり、Illustratorはアイコンやロゴなどのベクター作成に適しています。
Figmaは近年主流になっているUIデザインツールで、共同編集やプロトタイピングにも対応しているため、現場での使用頻度が高く、早い段階で習得しておくべきツールと言えるでしょう。
学習方法としては、最初にFigmaの基本操作から始め、チュートリアルやテンプレートを使って模写を繰り返すのが効果的です。
PhotoshopやIllustratorは、無料トライアルを利用しながら実務に近い課題(バナー制作やサムネイル作成)を通じて学ぶと、理解が深まります。
②コーディングスキル(HTML/CSS、JavaScriptなど)
Webデザイナーには「見た目を作る」だけでなく、「Web上に表示する」ための基礎的なコーディングスキルも求められます。
特にHTMLとCSSの理解は必須であり、静的なWebページを作れるようになることで、自分のデザインを忠実に再現する力が身につきます。HTMLはページの構造、CSSは見た目の装飾を担当するため、デザインを形にする上で切っても切れない存在です。
また、JavaScriptを学べば、スライダーやモーダルウィンドウ、スクロールアニメーションなどの動きのある表現も可能になります。JavaScriptは少し難易度が上がりますが、最初はライブラリ(jQueryなど)を使った簡単な実装から始めるとスムーズです。
独学で学ぶ場合は、「Progate」や「ドットインストール」などの初学者向けサービスを使いながら、簡単なWebページを模写することで習得が進みます。デザインと同時並行で学んでおくことで、即戦力としての評価も高まります。
③UI/UXの基礎知識
「見た目が良いだけ」では通用しないのが、現代のWebデザインです。
ユーザーが直感的に使いやすく、ストレスなく目的を達成できるような設計が求められるため、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)の視点を持つことが極めて重要です。
UIとは、ボタンやナビゲーションの配置、フォームの入力しやすさなど、実際の見た目に関する設計です。UXは、ユーザーの感情や行動フロー全体を考えた設計思想であり、「目的にたどり着きやすいか」「ストレスなく情報が見つかるか」などがポイントになります。
学習には、「UI/UXデザインの原則」に関する本や記事、優れたWebサイトのレビュー記事を読むことが有効です。FigmaやAdobe XDを使ったプロトタイピングを通じて、「体験」を設計する感覚を身につけることもおすすめです。
④SEOやマーケティングの基礎知識もあると強い
Webサイトの目的は、ただ綺麗な見た目を作ることではなく、ユーザーにアクションを起こしてもらうことです。そのため、検索エンジンでの集客(SEO)や、ユーザーを引き込む導線設計といったマーケティング視点も大切になります。
例えば、見出しタグの使い方、画像のalt属性、読み込み速度に配慮したデザインなど、SEOに強いデザインは結果的に「成果の出るWebサイト」につながります。
また、CTA(Call To Action)の配置や訴求の工夫、LPO(ランディングページ最適化)といった概念も、マーケティングを意識したデザインには欠かせません。
マーケティングに関しては、Web制作案件をこなす中で自然と求められるようになるスキルですが、基礎的なSEO用語や考え方だけでも先に押さえておくと、企業からの評価が上がります。
YouTubeやSEOブログなどでの学習が有効です。
⑤スキル習得にかかる期間の目安
未経験からWebデザイナーとしての基本的なスキルを一通り身につけるには、学習方法や時間のかけ方にもよりますが、おおよそ3ヶ月〜6ヶ月が一つの目安となります。
- 週10〜15時間程度の学習を継続できる場合
→約6ヶ月で実務レベルに到達可能 - 集中的に毎日学習できる場合
→約3ヶ月でポートフォリオ完成・転職活動可能
もちろん、PhotoshopやFigmaに触れた経験がある、HTML/CSSを少しかじったことがあるなど、過去の知識によっても進み具合は異なります。
また、スクールに通うことで独学よりも効率よく習得できるケースもあります。
大切なのは、「学習の順番」を意識して、基礎から積み上げることです。
焦らず段階的にスキルを身につけていけば、未経験でも確実にWebデザイナーとしての道を開くことができるでしょう。
Webデザイナーになるには独学とスクールどっちがいい?学習方法を比較
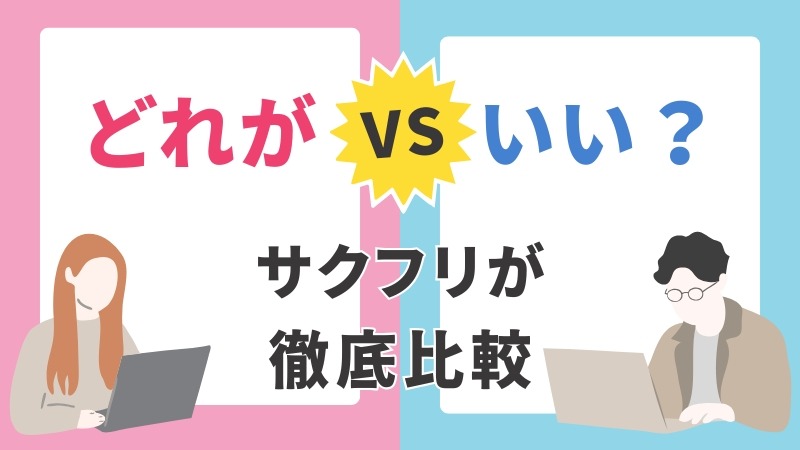
Webデザイナーを目指すうえで、多くの人が最初に悩むのが「独学で学ぶか」「スクールに通うか」という学習方法の選択です。
どちらにもメリット・デメリットがあり、自分の性格や生活スタイル、目的に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの違いを具体的に比較し、学習の方向性を明確にするための判断材料をご紹介します。
①独学のメリット・デメリット
独学の最大のメリットは、「コストが抑えられること」と「自分のペースで進められること」です。
YouTubeや書籍、ブログ、無料ツールなど、インターネット上には多くの学習コンテンツが揃っており、それらを活用すればほぼ無料〜低予算でスキルを習得できます。
また、自分の都合に合わせて時間を調整できるため、仕事や家事と並行して学びやすいのも魅力です。
一方で、最大のデメリットは「学習の迷子になりやすい」点です。
情報が多すぎて何から学ぶべきか分からなくなったり、モチベーションの維持が難しくなったりと、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
また、フィードバックがもらえないため、自分のデザインが適切かどうかを客観的に判断しづらく、成長が鈍化しやすいというリスクもあります。
②スクールに通うメリット・デメリット
Webデザインスクールに通う最大のメリットは、「カリキュラムが体系的に整っており、効率的に学べること」です。
未経験者がつまずきやすいポイントや、現場で必要とされるスキルに絞った指導が受けられるため、短期間で実務レベルに到達しやすくなります。
さらに、講師からのフィードバックや現役デザイナーによる添削、就職サポートなど、独学では得られない手厚い支援が受けられるのも大きな魅力です。
ただし、デメリットとしては「受講料が高額になりやすい」という点が挙げられます。スクールによっては20〜60万円以上かかる場合もあり、簡単には決断できない費用感です。
また、カリキュラムに沿って学習が進むため、自分のペースで進めたい人にとってはやや窮屈に感じることもあります。
サクフリでおすすめしているWebデザインスクールを知りたい方は、関連記事『Webデザインスクールおすすめランキング』をご覧ください。
③向いている人のタイプ別おすすめ
学習方法の選択は、性格や目的によって最適なものが変わります。以下に、向いているタイプ別のおすすめを紹介します。
独学が向いている人
- コストをできるだけ抑えたい人
- 自己管理能力が高く、計画的に学べる人
- すでにデザインやコーディングに触れたことがある人
- 自分の興味やペースで柔軟に進めたい人
スクールが向いている人
- 初めてWebデザインに触れる完全未経験者
- 最短でスキルを習得し、転職や副業に直結させたい人
- 一人では挫折しやすく、学習の継続が不安な人
- プロからのフィードバックや就職サポートが欲しい人
自分がどちらのタイプに近いかを見極めることが、遠回りせずにスキルを習得するための第一歩です。
④時間・費用・モチベーションの観点で比較
学習方法を選ぶ上では、「時間」「費用」「モチベーション維持」の3つの観点も非常に重要です。以下に比較をまとめます。
時間
独学は自分のペースで進められる分、学習がダラダラと長引いてしまうリスクがあります。スクールは期間が決まっているため、短期集中で取り組めるのが強みです。
費用
独学はほぼ無料〜数千円で始められるのに対し、スクールは数十万円かかるのが一般的です。
ただし、スクールは投資として回収しやすい場合もあり、就職や副業成功率が高い傾向があります。
モチベーション
独学は孤独になりがちで、途中で挫折するケースも多く見られます。スクールは講師や仲間と一緒に学ぶ環境があるため、継続しやすく、学習への熱も保ちやすくなります。
結論としては、「目的」「性格」「環境」によって最適な学習方法は異なるということです。
時間に余裕があり、マイペースに学びたいなら独学でも十分可能ですが、短期間で確実にスキルを習得したい、プロのサポートを受けながら安心して進めたいという方にはスクールの方が向いていると言えるでしょう。
Webデザイナーのポートフォリオの作り方:未経験でも評価される作品とは

Webデザイナーを目指す上で欠かせないのが「ポートフォリオ」の存在です。
どれだけスキルを学んでも、それを「可視化」し「伝える」ことができなければ、採用担当者やクライアントには評価されません。特に未経験者の場合、実務経験がないぶん、ポートフォリオの完成度が選考の大きな判断材料になります。
ここでは、未経験者でも評価されるポートフォリオの作り方について、目的・内容・制作手順・公開方法まで詳しく解説します。
①ポートフォリオの重要性と役割
ポートフォリオとは、自分のスキルやセンス、思考力を第三者に伝えるための「作品集」であり、Webデザイナーにとっての“履歴書”とも言える存在です。
履歴書や職務経歴書では伝わらない「視覚的な表現力」や「ユーザー視点の設計力」をアピールできるため、採用や案件獲得の成否を左右する重要なツールとなります。
また、ポートフォリオは単に「作品を並べるだけ」ではなく、自分がどのような考え方でデザインを制作したのか、どんなターゲットに向けて何を表現しようとしたのかといった「思考プロセス」を含めて伝えることが求められます。
そのため、見た目の完成度だけでなく、構成や説明の仕方によっても評価が大きく変わってくるのです。
②採用担当が見るポイント
ポートフォリオを評価する際に、採用担当者が注目するのは以下のような点です。
- 基本的なデザインスキルが備わっているか
→色使いや余白のバランス、フォント選び、視線の流れなど、デザインの基礎が理解できているかは必ずチェックされます。 - 目的に沿った設計ができているか
→単に「綺麗なデザイン」よりも、目的やターゲットに合った設計になっているかどうかが重要です。例えば、カフェのサイトなら温かみのある雰囲気、コーポレートサイトなら信頼感を意識したデザインが求められます。 - スマホ対応・レスポンシブデザインに対応しているか
→現在のWebサイトはモバイルファーストが当たり前。スマホでも見やすく作られているかは、未経験者であっても見られるポイントです。 - UI/UXの視点を持っているか
→ボタンの配置や操作性、ナビゲーションのわかりやすさなど、使いやすさへの配慮があるかどうかも大切です。 - 自分の言葉で説明できているか
→なぜこのデザインにしたのか、どう工夫したのかを文章で伝えられているか。デザイナーとしての考え方が垣間見える構成が好印象です。
③未経験者でも作れるおすすめテーマ・ネタ例
実務経験がない人でも、架空の案件を想定したポートフォリオは十分に評価されます。以下は、未経験者でも取り組みやすく、採用側にもイメージしやすいおすすめテーマです。
- 架空のカフェや飲食店のLP(ランディングページ)
- 自分のプロフィールサイト(自己紹介+作品掲載)
- 架空のアパレルブランドECサイトのトップページ
- 地域の観光紹介サイトのデザイン提案
- 実在のサイトをリデザインして改善案を提示する
重要なのは「目的とターゲットを設定して、その目的を達成するにはどんなデザインが必要か」という観点を持って取り組むことです。
また、1つのデザインだけでなく、3〜5作品程度は用意しておくと、バリエーションや成長過程が伝わりやすくなります。
④Web上に公開する方法(WordPress・STUDIOなど)
ポートフォリオはPDFや画像データではなく、Webサイトとして公開するのが主流です。
自分自身を「Webデザイナーとして見せる」ためにも、Web上での見せ方がそのままスキルの証明になります。
おすすめの公開方法
- STUDIO
→ノーコードで直感的にデザインでき、見た目も美しく仕上がる。初心者に最もおすすめ。 - WordPress
→自由度が高く、ブログ機能も付けたい人に最適。オリジナルテーマの適用も可能。 - Wix・ペライチ
→操作が簡単で、短期間で完成できる。無料プランもありコストを抑えられる。 - GitHub PagesやVercel
→コーディング力を見せたい人向け。HTML/CSS/JSをそのまま使える。
Web上にポートフォリオを公開する際は、独自ドメインの取得やGoogle検索へのインデックス登録をしておくと、よりプロフェッショナルな印象を与えられます。
また、URLを転職エージェントやクラウドソーシングのプロフィールに記載すれば、案件獲得にもつながりやすくなります。
未経験でも工夫次第で高評価を得られるポートフォリオは十分に作成可能です。
重要なのは「作ること」そのものではなく、「どう見せるか」「何を伝えたいか」を意識して取り組むこと。ポートフォリオは、自分の成長の記録であり、未来の仕事を呼び込む最大の武器になります。
Webデザイナーとして転職するには?成功のコツと求人の探し方
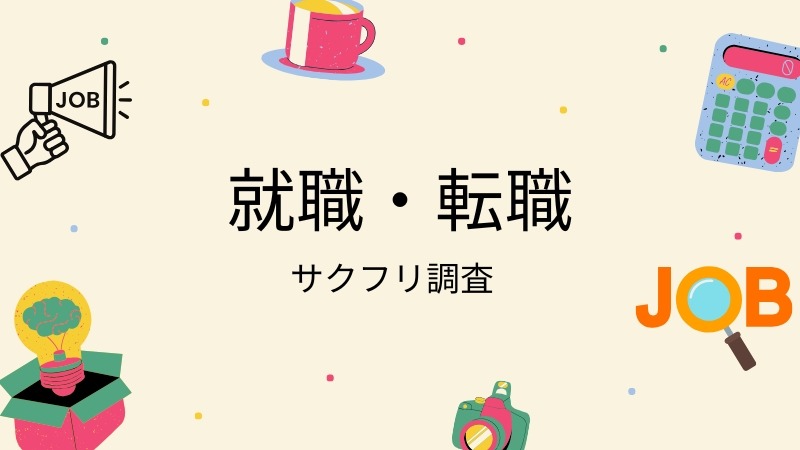
Webデザイナーとしてのスキルを習得した後、転職を目指す方も多いでしょう。
しかし、未経験からの転職は「求人の探し方がわからない」「ポートフォリオをどう見せればいいか不安」「面接で何を聞かれるのか想像がつかない」といった不安もつきものです。
ここでは、Webデザイナーとして転職を成功させるための具体的なコツや、求人の探し方について、未経験者の視点から丁寧に解説していきます。
①未経験OKの求人を見つけるコツ
未経験からWebデザイナーとして採用されるためには、「未経験OK」「ポテンシャル採用」といったキーワードが含まれた求人を見極めることが第一歩です。
ただし、表面的に「未経験可」と書かれていても、実質的には即戦力を求めているケースもあるため、募集要項を読み解く力が重要になります。
チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 「職業訓練卒歓迎」「ポートフォリオ提出必須」など、学習者を想定している文言がある
- 実務経験年数の条件がない、または「目安」とされている
- アシスタントデザイナーやHTMLコーダーとしての募集で、成長前提のポジションが明記されている
- 研修制度や教育体制が整っていることが強調されている
また、スタートアップや制作会社などでは、熱意や実務外の経験を評価してくれる場合も多く、自主制作のポートフォリオや積極的なアプローチが功を奏しやすい傾向にあります。
②ポートフォリオの提出タイミングと内容
ポートフォリオは「履歴書よりも重要」と言われるほど、Webデザイナーの選考では重視されるポイントです。
提出のタイミングとしては、書類選考時に提出するのが基本ですが、場合によっては面接時に持参するケースもあります。
オンラインポートフォリオであれば、応募時にURLを記載しておくことで企業側に事前に確認してもらえるため、チャンスを逃さずに済みます。
提出するポートフォリオの内容としては、以下を意識しましょう。
- デザインの目的・ターゲット・設計意図を明記する
- スマホ対応やUI設計の工夫がわかるようにする
- 3〜5作品程度のボリュームを目安に、多様なジャンルを見せる
- 自己紹介・スキル一覧・ツール使用歴なども掲載しておく
未経験であっても、「考えて作った」ことが伝わる構成にすることで、実務経験に勝る評価を得られることも珍しくありません。
③面接でよく聞かれる質問と回答例
Webデザイナーの面接では、スキルだけでなく「思考力」「コミュニケーション力」「主体性」なども重視されます。
以下は、未経験者がよく聞かれる質問と、それに対する回答のポイントです。
- 「なぜWebデザイナーを目指したのですか?」
→ 「自身でサイトを作るうちにデザインの奥深さに魅了された」「ユーザー視点で課題解決できる職業だと感じた」など、きっかけと志向を具体的に語ると好印象です。 - 「どんなデザインが得意ですか?」
→ 「余白を活かしたシンプルなUI設計が得意です」「女性向け商材の柔らかいデザインに自信があります」など、自身のスタイルを明確に言語化できると評価されます。 - 「どのように学習しましたか?苦労したことは?」
→ 独学やスクールでの具体的な取り組み、課題に対する解決姿勢を伝えることで、成長意欲が伝わります。 - 「今後どのようにキャリアを築きたいですか?」
→ 「まずはアシスタントから始めて、将来的にはディレクションにも関わりたい」など、成長意欲を感じさせると好印象です。
どの質問にも共通するのは、「自分の言葉で語れること」と「実体験をもとに話すこと」です。練習を重ねて、自然に話せるように準備しておきましょう。
④転職に強いエージェントやサイトの活用法
未経験からWebデザイナーに転職する場合、転職エージェントや専門サイトを活用することで、効率的に内定へ近づけます。
以下は、特に未経験・若手・クリエイティブ領域に強いとされる代表的なサービスです。
1.まず登録すべき転職サービス
まずは、下記で紹介する転職サービスに登録して、エージェントと面接を受けてみましょう。
エージェントとの面接を受けてみることで、自分の現在位置を把握することができますし、企業が求めているスキルやレベル感を把握することができます。
この時点では、あなたが思っている以上に採用レベルとの乖離に落ち込むことが多いと思いますが、皆さん、そうなりますので気にしないでOKです。
登録必須の転職サイト
登録必須の転職エージェント
- ユニゾンキャリア
→未経験者の就業決定率95%と高く最短3日でスピード内定が可能(20歳〜29歳) - UZUZ既卒
→既卒・フリーター向けのIT業界に強い転職エージェント(18歳〜29歳) - type転職エージェント
→IT・営業・ハイクラスの転職に強くコンサルタントを指名できる(30代以上もOK) - type女性の転職エージェント
→専任アドバイザーが女性のライフイベントに寄り添う老舗(30代以上もOK) - LHH転職エージェント
→外資系・日系大手のデザイン組織の求人に強い(30代以上もOK) - オカネコ転職
→第二新卒・未経験でも転職のプロが伴走して正社員を目指せる(30代以上もOK)
2.初心者レベルの知識を習得した人向けの転職サービス
続いては、初心者レベルの知識を習得した段階で登録すべきおすすめの転職サービスを紹介します。
ここからが本格的な転職活動になると思うので、Webデザイナーになるために、現実的に転職できる可能性が高い求人を紹介してくれる転職サービスに登録していきましょう。
ちなみに、「初心者レベルの知識を習得したレベル」=「Webスクールや職業訓練校のカリキュラムを一通り終了した人」と認識しておきましょう。
このレベルになれば、Webデザイナー初心者として具体的な求人を紹介してくれるようになるはずです。
登録推奨の転職エージェント
- LIGエージェント
→現役Web制作会社が運営で多種多様なクリエイター職種が用意(30代以上もOK) - マイナビクリエイター
→IT・ゲーム業界の求人に特化でポートフォリオ支援あり(30代以上もOK) - マスメディアン
→クリエイターからプロモーション職まで幅広く対応(30代以上もOK)
3.Webデザイナー以外の転職先に目を向ける時に登録すべきサービス
「2.初心者レベルの知識を習得した人向けの転職サービス」のフェーズで、Webデザイナーとして転職が叶った方はおめでとうございます。
あなたは相当優秀ですし、約3割の人材に入ります。一方、約7割の方は、理想通りに転職活動が進まないと思います。全く落ち込む必要はないですし、それが普通です。
そんな方は、1度、Webデザイナーとしてではなく、Webデザイナーへのキャリアップを目指せる、Webデザイナーに近しい職種へ転職することをおすすめします。
ちなみに、Webデザイナーへのキャリアップを目指せる、Webデザイナーに近しい職種とは、下記などが挙げられます。
Webデザイナーに近しい職種
HTML/CSSコーダー、ノーコードエンジニア、QAエンジニア、テクニカルライター、DTPオペレーター、バナー/LPデザイナー、CMS運用者、Web更新担当、SNS運用担当、Web広告オペレーター、メールマーケティング担当、インサイドセールス、編集アシスタント、SEOリサーチャー、テクニカルライター、SNSコピーライター、広報・Web担当事務、営業事務(提案資料作成)、EC運営アシスタント、秘書・アシスタント系職など
Webデザイナーに近い職種へ転職する最大のメリットは、「実務の中で自然にWebデザインの基礎や関連スキルを習得できる環境に入れること」です。
完全未経験からいきなりWebデザイナーを目指すよりも、コーダー・バナー制作者・SNS運用・ライターなどの職種で、徐々にUIやビジュアル、ユーザー視点を学びながら実績を積める方が、現実的かつ採用側にも評価されやすいルートです。
たとえば、コーダー職ではデザインの構造やツールに慣れながら「実装できるデザイナー」へ、バナー制作者ならマーケ視点を持った「CVに強いデザイナー」へ成長できます。
SNSやマーケ職ではユーザー導線やCVR改善に触れることで、UXを意識したデザイン提案力が身につきます。ライター職なら情報設計や構成力が武器になり、ワイヤーフレームやUI設計への応用が可能です。
営業事務として提案資料やプレゼン資料を多く作っている人は、情報を見やすく整理し、相手の理解度を考えて構成するという、情報設計のスキルをすでに日常的に使っています。
これは、WebデザイナーがUIを設計する際の考え方と非常に近いものです。ここにFigmaなどのツール操作を加えれば、「伝わる資料」を作っていた人が「伝わるWebページ」を作る存在へと進化できます。
これらの職種に共通するのは、「デザインに必要な一部のスキルや視点をすでに持っている」という点。そこにツール習得とポートフォリオ制作を加えれば、「未経験」ではなく「隣接実務経験者」としてWebデザイナーを目指せます。
段階的なキャリア設計の方が習得の再現性も高く、結果的に強みのあるデザイナーとして市場で評価されやすくなります。
そのため、まずは「3.Webデザイナー以外の転職先に目を向ける時」は下記のサービスに登録しておきましょう。
登録必須の転職エージェント
- リクルートエージェント
→求人数最多、非公開含め幅広く網羅できる万能型(30代以上もOK) - マイナビエージェント
→全国対応!面接対策や書類添削もフルサポート(30代以上もOK) - ツナグバ
→未経験OKの企業を中心に20・30代の第二新卒の転職に特化(18歳〜33歳) - ジムノミカタ
→既卒・フリーター歓迎!事務職に特化した転職サービス(20歳〜32歳)
登録推奨の転職エージェント
- Re就活エージェント
→第二新卒・既卒・フリーター向け転職エージェント(20歳〜29歳) - 第二新卒エージェントneo
→第二/既卒/フリーター/中退/高卒の就職・転職支援に特化(18歳〜29歳) - ジールエージェント
→20代・未経験の転職に特化で最短2週間のスピード転職が可能(20歳〜29歳) - アメキャリ
→フリーターや第二新卒向けで未経験OKの求人が60%以上(18歳〜29歳) - チアエージェント
→ベンチャー・成長企業に特化で既卒・第二新卒・フリーター向け(20歳〜29歳) - ハタラクティブ
→既卒・フリーターなどの未経験者の転職に特化(18歳〜29歳) - ミラフリ
→20代フリーターの就職・転職に特化した転職エージェント(20歳〜29歳) - キャリアパーク就職エージェント
→選考通過率アップ支援の取り組みが充実(20歳〜29歳) - ミラキャリ
→20代未経験からの事務職転職に特化した転職支援(18歳〜29歳)
まとめ:Webデザイナーへの転職への道
以上、Webデザイナーを目指す方におすすめの転職サービスでした。
未経験からのWebデザイナー転職は、確かにハードルがある一方で、準備さえ整えば多くのチャンスがあります。
大切なのは「ポートフォリオで伝えること」「志望動機に一貫性を持たせること」「適切なサポートを受けること」。
これらを押さえておけば、未経験でも十分に採用を勝ち取ることが可能です。
サクフリでおすすめしている転職エージェントを知りたい方は、関連記事『Webデザイナー職向けの転職エージェント』をご覧ください。
Webデザイナーとして副業で稼ぐには?収入の目安や案件の獲得方法
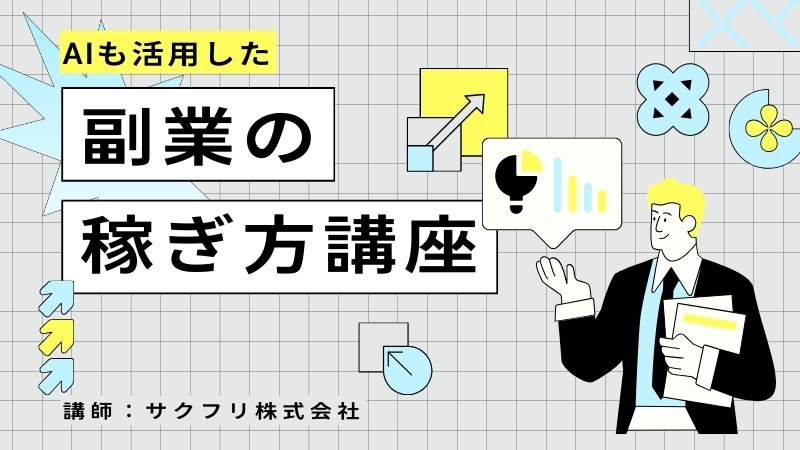
Webデザインのスキルは、副業として非常に相性の良いジャンルです。
在宅で作業できる案件が多く、単発でも継続でも対応しやすいため、会社員や主婦の方、副業初心者にとっても挑戦しやすい分野だと言えます。
ここでは、副業Webデザイナーとして収入を得るための方法や、案件獲得のコツ、具体的な収入の目安について詳しく解説していきます。
①副業Webデザイナーの働き方と収入例
副業でWebデザインを行う場合、働き方は非常に柔軟です。
平日の夜や週末を活用して作業することができ、納期の調整もしやすいため、本業と両立しながら収入を得ることが可能です。
特に在宅でできる案件が多いため、場所に縛られずに働けるのも魅力です。
副業Webデザイナーの主な収入例
- バナー制作:1枚あたり3,000〜10,000円程度
- LPデザイン:1ページあたり30,000〜80,000円程度
- サイト全体のデザイン・コーディング:100,000円〜300,000円以上も可能
- Webメディアのアイキャッチ画像制作:1枚あたり1,000〜3,000円
実際には、月3〜5万円程度からスタートして、実績を積めば10万円以上の副収入も十分に可能です。中には副業からスタートして、そのまま独立・フリーランスへ移行する人も少なくありません。
②案件の探し方(クラウドソーシング・SNSなど)
副業として案件を受けるためには、まず「どこで仕事を探すか」が重要になります。以下のような方法を組み合わせることで、未経験者でも案件を獲得しやすくなります。
クラウドソーシングサイト
クラウドソーシングサイト
これらのサービスでは、「バナー制作」「LP制作」「ECサイトの画像作成」など、初心者向けの案件も数多く掲載されています。
最初は単価が低めでも、実績を積むことで信頼を得られ、継続案件や指名依頼につながることもあります。
サクフリでおすすめしているクラウドソーシングサービスを知りたい方は、関連記事『副業初心者向けクラウドソーシングおすすめ比較ランキング』をご覧ください。
SNS(主にX / Instagram)
X(旧Twitter)やInstagramなどでは、「#デザイナー募集」「#Webデザイン」などのハッシュタグを使って、個人や企業が直接案件を募集していることもあります。
日々の発信やポートフォリオをSNSで継続的に見せることで、案件依頼を受けるチャンスが生まれることもあるため、実績が少ないうちはSNS活用が特に効果的です。
知人・友人からの紹介
小規模な店舗や個人事業主など、周囲に「Webサイトを作りたいけど誰に頼めばいいか分からない」と悩んでいる人は意外と多いものです。
身近な人に「Webデザインを勉強していて、実績づくりをしたい」と伝えることで、思わぬ依頼につながることもあります。
③副業でよくあるトラブルと対策
副業としてWebデザインをする際には、いくつかの注意点もあります。特に以下のようなトラブルには気をつけましょう。
- 無理な納期でスケジュールが崩れる
→ 受注前に必ず納期を確認し、自分の時間と照らし合わせて無理がないかを見極めましょう。 - 報酬の未払い
→ 契約書を交わす、クラウドソーシング経由で安全にやり取りするなど、トラブル防止策を講じましょう。 - 業務範囲があいまいで、無償対応を求められる
→ 最初の段階で業務範囲を明確にし、追加対応は別料金と提示しておくことが大切です。 - 本業の就業規則に抵触する
→ 会社員の方は、副業が許可されているかを事前に確認しておきましょう。副業届の提出が必要な場合もあります。
副業は自由度が高い反面、自分自身で案件の管理・交渉・納品までを行う必要があります。だからこそ、「自己管理力」や「ビジネス的な意識」も重要になります。
④実績ゼロから案件を獲得する方法
未経験・実績ゼロの状態でも、工夫次第で副業案件を獲得することは可能です。以下のようなアプローチを試してみましょう。
- ポートフォリオサイトを公開する
→ 架空の案件でもよいので、3〜5作品を掲載したポートフォリオサイトを作成して信頼性を高めましょう。 - 「実績作り価格」で仕事を受ける
→ 最初は低単価でも構わないので、「実績を作りたいので格安で対応します」とSNSやクラウドソーシングでアピールする戦略も有効です。 - スクールで作った作品を掲載し、学習歴を伝える
→ スクール卒であることを明記し、「体系的に学んできた」とアピールすると安心感につながります。 - CanvaやSTUDIOを活用して素早く提案する
→ 相手にイメージを見せることで、言葉だけの提案よりも受注率が格段に上がります。
副業としてWebデザイナーに挑戦するのは、今の時代に非常に合った選択肢です。
最初は小さな案件から始めて、実績を積み重ねることで、安定した副収入や、将来的な独立にもつながっていきます。
自分のスキルを少しずつ可視化し、適切な場所で発信し続けることが、案件獲得と継続の鍵になります。
Webデザイナーとして独立するには?必要な準備と収入アップのコツ

副業や転職を経て、最終的にフリーランスとして独立を目指すWebデザイナーは少なくありません。
フリーランスになることで、働く場所や時間を自由に選べるだけでなく、案件選びや収入面でも大きな裁量を持つことができます。一方で、安定性や営業力なども問われるため、しっかりと準備を整えておくことが重要です。
ここでは、Webデザイナーとしてフリーランス・独立を目指すために必要な準備や、収入アップを実現するための具体的なポイントについて詳しく解説します。
①開業前に必要な準備・手続き
フリーランスとして活動を開始するには、まずは最低限の開業手続きや環境整備が必要です。
まず行うべきは、税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出することです。
これにより、正式に個人事業主として認められ、屋号の使用や青色申告の適用などが可能になります。開業届は無料で提出でき、郵送でも受け付けてもらえます。
次に準備しておきたいのが、業務に必要なツールと作業環境です。主なものは以下の通りです。
- デザインツール(Figma、Photoshop、Illustratorなど)
- コーディング環境(VS Code、FTPソフト、ブラウザ検証ツールなど)
- 業務管理ツール(Googleカレンダー、Notion、請求書発行ソフトなど)
- オンラインポートフォリオサイト(自己紹介+実績掲載ページ)
加えて、名刺やSNS、連絡用メールアドレス、請求書フォーマットなどの整備もしておくと、信頼感のある対応が可能になります。
また、会計処理に関しては「freee」や「マネーフォワード クラウド会計」などのクラウド会計ソフトを活用すると、確定申告や経費管理が格段に楽になります。
②営業活動のやり方と案件の広げ方
フリーランスにとって重要なのが「案件を継続的に受注する営業力」です。
最初のうちは知名度がなく、実績も少ないため、仕事を得るには積極的な発信と行動が欠かせません。営業方法には以下のようなものがあります。
- フリーランスエージェントの継続活用(レバテッククリエイターなど)
- Web制作会社や広告代理店へのメール営業・ポートフォリオ送付
- SNS(X、Instagram)での定期的な発信と実績紹介
- ポートフォリオサイトに「制作依頼フォーム」や「料金表」を設置
- 既存クライアントからの紹介を受けるための丁寧な納品と関係構築
特にやることが多い新米フリーランスにとっては、フリーランスエージェントに登録しておくのはおすすめです。
下記がWebデザイナーにおすすめの代表的なフリーランスエージェントになるので、全て登録しておくことをおすすめします。
フリーランスエージェント
- レバテッククリエイター
→デザイナーを始めとしたクリエイター向け案件数が業界最大 - フリコン
→企業・官公庁のデザイナー・ディレクター向け求人が豊富 - ギークスジョブ
→在宅案件やリモート案件が80%以上と多い - エンジニアルート
→40代・50代への案件紹介も可能でフリーランス初心者向け
営業のコツは「自分がどんな仕事が得意で、どんな価値を提供できるか」を明確に伝えること。
単に「仕事ください」と言うのではなく、「こういう分野のデザインに強みがあります」「過去にこういう改善実績があります」といったアプローチが効果的です。
サクフリでおすすめしているフリーランスエージェントを知りたい方は、関連記事『Webデザイナー向けフリーランスエージェント』をご覧ください。
③継続案件を得るためのコツ
フリーランスとして安定収入を得るためには、「単発の案件をいかに継続案件につなげるか」がカギになります。
一度納品したら終わりではなく、リピートや紹介につなげるためには、信頼と安心感のある対応が求められます。
継続につながるポイント
- 連絡を早く・丁寧に返す(レスポンスの速さは信頼につながる)
- 修正対応に柔軟に応じる(範囲内であれば好意的に対応)
- 制作意図や提案を明確に説明し、プロとしての姿勢を見せる
- 納品後も「不具合あればご連絡ください」とフォローする
- 適切なタイミングで「また何かあればお声がけください」と伝える
こうした細やかな対応が積み重なることで、「またお願いしたい」と思ってもらえる関係性が築けます。特に、保守や更新などの「月額固定での契約」を提案できると、収入の安定にもつながります。
④単価交渉のテクニックと注意点
フリーランスとして活動する上で、単価交渉は避けて通れないテーマです。特に初期の頃は「安く受けすぎてしまった」「値上げしたいけど言い出せない」といった悩みを抱えがちです。
単価交渉のコツ
- 「時給ベース」ではなく「成果ベース」で価値を伝える
- 市場相場や他案件との比較データをもとに説明する
- 初回は割安でも「2回目以降は正規料金になります」と事前に伝える
- 作業範囲や納期を明確にして、価格の理由を説明する
- 交渉のタイミングは「満足いただけた後」がベスト
注意点としては、感情的にならず、冷静に交渉を進めること。また、値下げを要求された場合は「どの範囲を削るか」も含めて丁寧に話し合う姿勢が重要です。
フリーランスWebデザイナーとして成功するには、「スキル」だけでなく「営業力」「対応力」「提案力」など、ビジネス的な要素も求められます。
しかし、それらはすべて行動と経験の中で身につけていけるものです。まずは副業や小さな案件から始めて、実績と自信を積み重ねていくことで、自由度の高い働き方と収入の両立が実現できます。
Webデザイナーの年収はどれくらい?雇用形態別に解説

Webデザイナーとして働くにあたって、「実際どれくらいの年収が見込めるのか」は多くの人が気になるポイントです。
特に未経験からキャリアをスタートする場合や、副業・フリーランスで働くことを検討している場合は、雇用形態ごとの収入の違いを正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、Webデザイナーの年収について、雇用形態別・地域別・スキル別の視点から詳しく解説します。
①正社員・派遣・業務委託・フリーランスの収入比較
Webデザイナーの年収は、雇用形態によって大きく異なります。以下に代表的な働き方ごとの平均的な年収目安を示します。
正社員
正社員Webデザイナーの年収は、おおよそ300万円〜500万円程度が相場です。
新卒や未経験の場合は年収250万円前後からのスタートもありますが、実務経験を積み、ディレクションやUI/UX設計など幅広いスキルを身につけていくことで、年収600万円以上を狙うことも可能です。
企業規模や業界によっても差があり、インハウス(自社サイト担当)よりも制作会社や広告代理店の方がやや高めの傾向があります。
派遣社員
派遣Webデザイナーは、時給ベースでの契約が主流です。
平均的な時給は1,500円〜2,200円程度で、月収換算で25万円〜35万円前後が目安になります。経験やスキルに応じて、高時給の案件を得ることも可能ですが、ボーナスや福利厚生がない分、年収は正社員よりやや低くなることが一般的です。
業務委託(準委任契約)
業務委託の場合は、稼働日数・時間によって単価が決まるケースが多く、週3日稼働で月25万〜35万円、週5日フル稼働で月50万円以上になることも珍しくありません。
エージェント経由での案件が多く、安定した報酬を得ながらもフリーランス的な自由度があるのが特徴です。
フリーランス
フリーランスWebデザイナーは、案件の単価や受注件数によって大きく収入が変動します。
実績を積んでいくことで、年収400万〜600万円以上を安定して得ている人も多く、月収でいえば30万〜80万円以上も可能です。継続案件や保守契約を複数持てば、さらに安定性が増します。
ただし、営業や経理、スケジュール管理などすべて自己責任となるため、事業者としての意識が必要です。
②地方と都市部での年収の違い
Webデザイナーの年収は、都市部と地方で大きな差があります。
東京・大阪・名古屋といった都市圏では求人も多く、デザインの質や納期に対する期待値も高いため、年収も相対的に高くなる傾向があります。
特に東京では、未経験でも月給25万円前後からスタートできる求人が見られる一方、地方では20万円前後が一般的ということも。
ただし、リモートワークが普及した現在では、地方に住みながら都市圏の案件を受注する働き方も一般的になっています。
これは特にフリーランスや業務委託で大きな武器となり、住居費を抑えながら都市部水準の収入を得ることも十分に可能です。
③スキルや実績による収入の伸び幅
Webデザイナーの収入は、スキルの深さや実績の質によって大きく伸びます。以下のようなスキルが加わることで、単価アップが狙えます。
- UI/UX設計スキル
→ユーザー視点で設計できるデザイナーは重宝される - コーディングスキル(HTML/CSS/JavaScript)
→デザインだけでなく構築まで対応できることで、単価が倍近くになることも - WordPress構築スキル
→中小企業のニーズに応えやすく、フリーランスとして案件を獲得しやすい - マーケティングやSEOの知識
→成果に貢献できるデザインは、長期案件や報酬アップにつながる
また、制作実績が増えることで、ポートフォリオの質が上がり、より単価の高い案件に挑戦しやすくなるのも大きなメリットです。
継続クライアントとの関係構築や、信頼性のある発信を行うことで、営業せずとも仕事が舞い込む状態をつくることも可能になります。
④副業や複業での収入アップ事例
本業を持ちながら副業としてWebデザインを行う人も増えており、そのスタイルでも十分な収入アップを実現している例が多く見られます。
- 月3件のバナー制作で月収3万〜5万円
- 単発のLP制作で月収5万円〜10万円
- 本業とは別に、週末のみの業務委託で月20万円を実現
こうした副業ベースからスタートし、実績と収入が安定してきた段階でフリーランスへ移行する人も多数存在します。初めから独立を目指すのではなく、副業→兼業→独立という段階的な進め方が現実的でおすすめです。
Webデザイナーの年収は、スキルと戦略次第で大きく伸ばせる可能性を秘めています。
「どのような働き方を選ぶか」「どの分野のスキルを磨くか」によって、キャリアの広がり方や収入の安定性は変わってきます。
自分のライフスタイルや価値観に合った道を見つけることで、Webデザインという仕事はより自由度の高い、魅力的なキャリアになっていくでしょう。
Webデザイナーに関するよくある質問【Q&A】
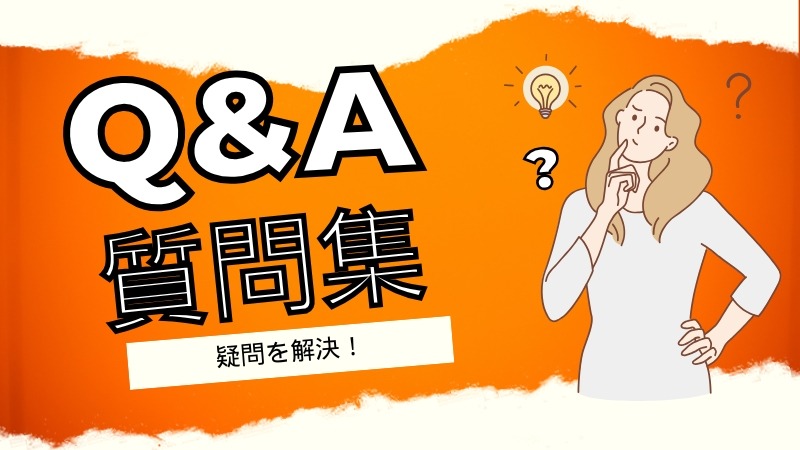
Webデザイナーを目指す人の多くが、年齢や経験、ライフスタイルに不安を感じています。
特に「完全な未経験」「30代からの転職」「子育て中の主婦」といった立場だと、「本当に自分でもなれるのか?」と疑問を抱くのは当然のことです。
しかし、Webデザインは年齢や経歴に左右されにくく、学習と努力によって誰にでもチャンスがある職業です。ここでは、よくある疑問について詳しく回答していきます。
①本当に未経験からなれる?年齢は関係ある?
結論から言うと、完全な未経験からでもWebデザイナーになることは十分に可能です。
実際、多くのスクールや転職エージェントでは、営業職・販売職・事務職など、異業種からの転職成功事例が数多く紹介されています。
年齢に関しても、20代〜30代はもちろん、40代で転職や副業を始めた人も珍しくありません。企業側も「スキル」「コミュニケーション力」「自己管理能力」などを総合的に評価するため、年齢だけで判断することはほとんどありません。
大切なのは、ポートフォリオや面接で「どれだけ本気で取り組んでいるか」「実際にどんなスキルがあるか」を伝えることです。
また、Web業界は新しいスキルやツールを自発的に学べる人材を歓迎する傾向があるため、未経験でも学習姿勢をしっかり示せば十分に評価されます。
②デザインセンスがなくても大丈夫?
「自分にはセンスがないから不安…」という声もよく聞かれますが、センスは“学べる”ものです。
最初からプロのようなデザインができる人はいませんし、むしろセンスよりも「基本的なルール」を理解していることが重要です。
たとえば、余白の取り方、フォントの使い分け、配色の基本、視線誘導の原則などは、きちんと学べば誰でも習得できる技術です。
実際に多くのプロデザイナーも、まずは「良いデザインを真似る」ことから始めています。Web上には模写用のデザインギャラリーや参考サイトが多数存在し、繰り返し真似していくことで自然と視覚的なバランス感覚が養われていきます。
つまり、「センスの有無」で諦める必要はまったくありません。正しい順序で練習すれば、誰でも着実にレベルアップできます。
③主婦や子育て中でも仕事はできる?
Webデザインは、在宅で完結できる仕事が多く、主婦や子育て中の方にも非常に適した職種です。
実際、在宅ワークやフルリモート案件が増えており、クラウドソーシングやフリーランスエージェントを通じて柔軟に働く主婦のWebデザイナーも多く存在します。
1日2〜3時間の稼働でも対応可能なバナー制作や更新作業などの案件もあり、育児の合間を縫って働けるのが大きなメリットです。
さらに、自宅でスキルアップできるため、空き時間を使って学習しながら、徐々に仕事の幅を広げていくこともできます。
注意点としては、「納期の管理」と「連絡のレスポンス」が求められるため、ある程度のスケジュール調整能力が必要です。
とはいえ、フルタイム勤務と比べて柔軟性が高く、ライフスタイルに合わせた働き方ができるのはWebデザインならではの強みです。
④就職とフリーランスはどっちがおすすめ?
「正社員として働くべきか、それともフリーランスを目指すべきか」は、多くの人が悩むポイントです。
結論としては、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の目的や価値観に応じて選ぶのが正解です。
正社員のメリット
- 安定した収入と福利厚生
- 実務経験を通じて成長できる
- チームでの制作や上流工程を学べる
フリーランスのメリット
- 働く時間や場所を自由に選べる
- 単価を自分で決められる
- 自分のペースで成長と収入アップが目指せる
未経験者の場合は、まず正社員や業務委託で実務経験を積むことをおすすめします。
その後、経験を活かしてフリーランスに移行することで、より高単価での案件受注や自由な働き方が実現しやすくなります。
Webデザイナーは、未経験・30代・主婦といった立場に関係なく、スキル次第で可能性が広がる職業です。
必要なのは「始めること」と「継続すること」。小さな一歩が、将来の働き方や収入を大きく変えるきっかけになります。年齢や状況に縛られず、まずは学びながら少しずつ挑戦してみましょう。
まとめ:Webデザイナーは人生を変えるキャリアの選択肢
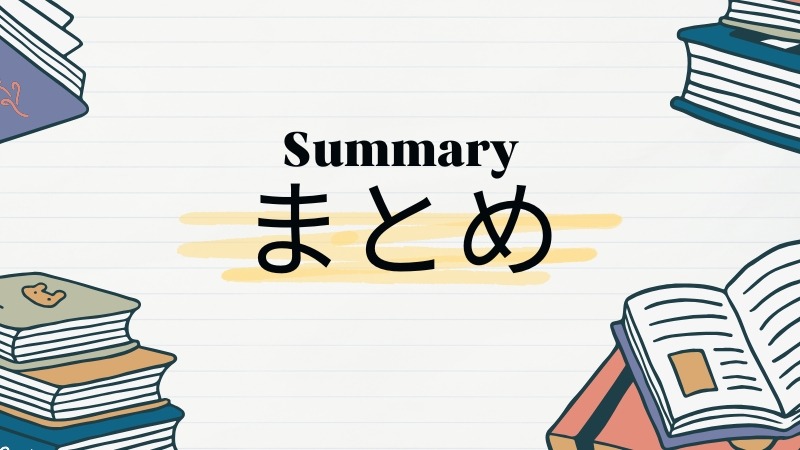
今回は、未経験からWebデザイナーになるための完全ロードマップを紹介しました。
Webデザイナーという職業は、年齢や経歴を問わず、多くの人にとって現実的なキャリアの選択肢です。
未経験からでも、正しい学習ステップを踏めばスキルを習得でき、転職や副業、さらにはフリーランスとして独立することも十分に可能です。しかもそのすべてが、比較的短期間で実現可能である点もWebデザインの大きな魅力と言えるでしょう。
デザインスキルやコーディング技術、UI/UXやマーケティングの知識は、どれも初めから備えている人はいません。
ですが、目的意識を持ち、地道に取り組んでいけば、必ず形になります。そして、それらのスキルを「ポートフォリオ」として可視化し、自分自身の価値を正しく伝えられるようになったとき、あなたは“仕事が取れるデザイナー”として確かな一歩を踏み出せているはずです。
働き方の面でも、Webデザイナーは非常に自由度が高く、ライフスタイルに合わせたキャリア設計が可能です。正社員として安定を得る道も、副業で月数万円の収入を得る道も、フリーランスとして月収50万円以上を目指す道もすべて現実的な選択肢です。
今、少しでもWebデザインに興味があるのなら、まずは手を動かしてみることから始めてください。環境も教材も、以前よりずっと整っています。
そして何よりも、あなたの「やってみたい」という気持ちが一番の原動力になります。
Webデザイナーという仕事は、ただ“作る”だけでなく、人の心を動かし、行動を促し、ビジネスの成果にもつながる、非常に価値あるスキルです。
これからのキャリアを考えるうえで、自分の力で道を切り拓けるこの仕事は、きっとあなたの人生を大きく変えるきっかけとなってくれるはずです。
今回は以上です。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。